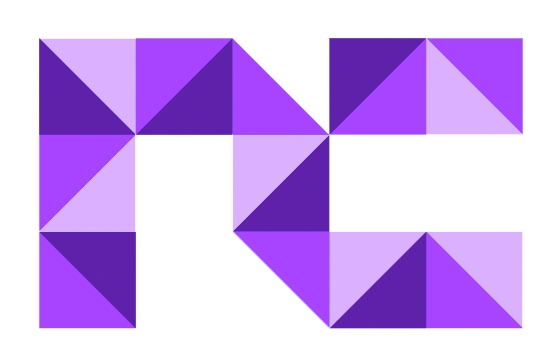一般社団法人ノーコード推進協会(NCPA)が提供する「ノーコードパスポート※1」は、ノーコードの基本的な知識と活用能力を証明するための認定資格です。企業のDXを推進する上で最も基礎的なデジタルスキルの習得に適しています。
今回はそのノーコードパスポートを社内の人材育成に活用されている株式会社ギガ(※2) ビジネスソリューション部を率いる宮﨑様、同部の杉田様、そして2025年4月に新卒で入社し、早速ノーコードパスポートを取得された田沼様にお話を伺いました。(インタビュアー:ノーコード推進協会 代表理事 中山 五輪男)
直感的にシステム開発の面白さや全体像を理解できる入り口が必要

中山: 本日はありがとうございます。早速ですが、貴社がノーコードに着目し、人材育成に取り入れようと考えた背景にある課題感についてお聞かせいただけますか。
宮﨑様: はい。我々のビジネスソリューション部では、新卒採用で文系出身者を多く採用しています。彼ら・彼女らが一日も早く開発の現場で活躍できるよう、効率的かつ体系的な育成方法を常に模索していました。従来のプログラミング言語の学習は、どうしても初期のハードルが高い側面があります。そこで、もっと直感的にシステム開発の面白さや全体像を理解できる「入り口」が必要だと感じていました。

杉田様: 経験則だけでスキルを伸ばすのには限界があります。特に公共系の入札案件などでは、技術者のスキルを客観的に証明するものが求められる場面が増えてきました。資格は、本人が「体系的に物事を学んだ」という証明になりますし、会社としても「ノーコードという新しい技術体系を理解し、資格を持った人材がこれだけいます」と具体的に示せることは、お客様からの信頼獲得やブランドイメージ向上に直結すると考えました。

報奨金制度でモチベーションアップ、全員でスキルアップを目指す
中山: 文系出身者が多い新入社員の育成に、ノーコードパスポートをどのように活用されているのでしょうか。
宮﨑様: まず、新人研修のカリキュラムにノーコードツールの実習を組み込んでいます。Javaなどの学習よりも取り組みやすいようで、好評ですね。座学だけでなく、実際に手を動かして簡単なアプリケーションを自分たちで企画・作成し、発表するまでを実践してもらいます。その上で、研修の総仕上げとしてノーコードパスポートの受験を推奨しています。
中山: 資格取得を支援する手厚い制度が、社員のモチベーションに繋がっていると伺いました。
宮﨑様: 受験料は会社が全額負担しています。これまでも様々な資格試験で受験費用の補助や報奨金の制度がありましたが、今年の4月からはノーコードパスポートもその制度に加えました。これは役職や経験に関係なく、頑張った人が正当に評価される文化を作りたかったからです。若手社員にとっては、これが大きなモチベーションになっているようです。
杉田様: 実は、私が社内で最初にノーコードパスポートを受験した一人なのですが、その時はまだ報奨金制度の対象ではなかったのです(笑)。でも、こうして制度が整い、後輩たちが目標を持って取り組める環境ができたのは本当に喜ばしいことです。資格という明確なゴールがあることで、日々の学習にも身が入りやすいという声を聞いています。
暗記ではなく、ノーコードの本質を学ぶことができる
中山: 田沼様は新卒で入社後すぐに受験されたとのことですが、試験の印象はいかがでしたか?

田沼様: はい。私は法学部出身で、趣味でゲーム制作ツールを触ったことはありましたが、業務としての開発は未経験でした。試験内容は単なる暗記問題ではなく、「ノーコードツールとはどういう考え方で、何を目指すものなのか」という本質的な理解を問うものが多く、非常に勉強になりました。
中山: 難易度についてはどう感じましたか?
田沼様: 難しすぎず、簡単すぎず、初学者にとってはちょうど良いレベル感だったと思います。Webサイトで公開されているテキストや動画教材をしっかり学習すれば、十分に合格点が取れる内容です。特に印象的だったのは、同じ趣旨の問いが少し角度を変えて繰り返し出題される点です。それによって自分の理解度を再確認でき、自信を持って解答を進めることができました。杉田様: 私の場合は、半分くらいの時間で回答と見直しまでできましたが、人によってはじっくり考える時間が必要かもしれませんね。いずれにせよ、ノーコード技術の特徴や開発における考え方を理解しているかどうかのチェックとして、非常に有用だと感じています。
ノーコードが実現する、従来とは全く異なる開発アプローチ
中山: ノーコード技術が広まることで、開発の進め方やお客様との関係性はどのように変わるとお考えですか。
宮﨑様: 開発の進め方については、従来のウォーターフォール型の開発では、要件定義から設計、開発、テストと進む中で、お客様が実際に動くものを目にするのは最後の工程でした。しかし、ノーコードを使えば、非常に早い段階で「動くプロトタイプ」をお見せできます。お客様とイメージを共有しながら進めていけるので、お客様の満足度も高いと感じております。お客様との関係性は先のように具体的なイメージを共有してプロジェクトが進みますので、課題の共有が多くなり、チームとしての一体感が強まっていると思っています。
杉田様: 従来のV字モデルとは全く違うアプローチですよね。「こういうイメージで合っていますか?」とプロトタイプを見せながら対話し、その場で修正し、また確認してもらう。このアジャイルなサイクルを高速で回せるのがノーコードの最大の強みです。これは単なる開発プロセスの変化ではなく、お客様を開発の「共創パートナー」として巻き込んでいく、新しい価値提供の形だと考えています。
AIエージェントが当たり前になる世界で価値を発揮するノーコードアプリケーション
中山: 最後に、ノーコードやAI技術の活用を含めた今後のビジョンについてお聞かせください。
宮﨑様: 我々は、お客様の課題に応じてプロコード、ローコード、ノーコードを最適に組み合わせ、お客様の課題を共有し、解決する技術者集団でありたいと考えています。その中で、ノーコードは特に業務改善の初動や、市民開発を支援する領域でさらに活用が進むでしょう。
杉田様: 現場レベルでは、すでにGitHub CopilotのようなAIアシスタントの活用を始めています。特に弊社はゼロからの開発だけでなく、既存システムの仕様変更や改修も多いのですが、AIを使えば影響範囲の分析などが格段に速くなります。将来的には、「こういう業務を自動化したい」とAIエージェントに指示するだけで、裏側でノーコードツールが連携してアプリを自動生成する世界が来るはずです。その時に備え、今のうちから現場にたくさんのノーコードアプリを蓄積しておくことが重要だと考えています。
中山: 田沼様は、今後どのようなスキルを身につけていきたいですか?
田沼様: まずは「ITパスポート試験」や「基本情報技術者試験」といった基礎を固めつつ、ノーコードで学んだ「課題を解決するためにシステムをどう組み立てるか」という考え方を応用していきたいです。将来的には、AIの技術も学び、お客様の課題解決に貢献できるエンジニアになりたいと思っています。

まとめ
株式会社ギガ様は、「ノーコードパスポート」を単なる資格としてではなく、文系出身者をはじめとする若手人材がDXの最前線で活躍するための「入り口」と位置づけ、戦略的に活用されています。手厚い支援制度と実践的な研修を組み合わせることで、社員のモチベーションを高め、わずか1年足らずで20名以上の合格者を輩出。今年度の目標である30名達成も目前に迫っています。
「プロトタイプを介した顧客との共創」「AIエージェント時代への備え」といった同社の先進的なビジョンは、これからのDX時代におけるSIerの新たな役割を示唆しています。経営層の戦略、現場の推進力、そして若手の意欲が見事に噛み合ったギガ様の人材育成戦略は、多くの日本企業にとって、DX推進と人材育成を両立させるための優れたモデルケースとなるでしょう。
※1:ノーコードパスポートについて
ノーコードパスポートは、一般社団法人ノーコード推進協会(NCPA)が提供する、ノーコードの基本的な知識と活用能力を証明するための認定資格です。DXを推進する上で不可欠な、業務改善やアプリケーション開発の基礎スキルを持つ人材であることを客観的に示します。
プログラミング経験のないビジネスパーソンや学生でも、体系的な学習を通じてノーコードの概念、ツールの特性、開発プロセス、業務への活用方法などを習得できるように設計されており、企業のDX人材育成や、個人のリスキリングの第一歩として注目されています。
※2:株式会社ギガ様について
株式会社ギガ様は、ICTサービスで社会課題を解決するソーシャル・ソリューションメーカー「コアグループ」に属する、ビジネスエンジニアリング企業です。約160名の従業員を擁し、「ネットワークソリューション事業」と「ビジネスソリューション事業」を2つの柱として事業を展開しています。従来のスクラッチ開発やパッケージソフトの周辺開発に加え、約3年前から開発のスピードと柔軟性を高めるため、ノーコード・ローコードツールの活用に着目。オープンソースのツールなどを積極的に導入し、変化の速い市場のニーズに応え続けています。
特に、新卒採用では文系出身者を積極的に採用しており、未経験からでも早期に戦力化できる独自の育成プログラムを構築。その一環として「ノーコードパスポート」の取得を全社的に推進し、DX時代に対応できる技術者集団への変革を進めています。