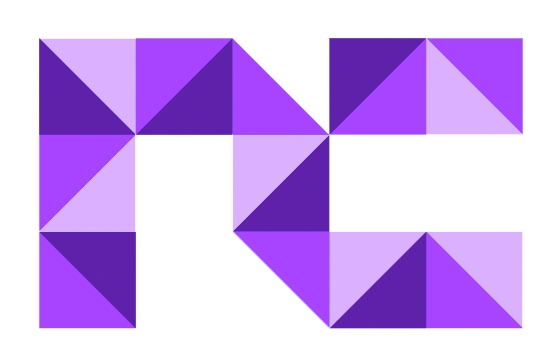【2/7開催】NO CODE SYMPOSIUM 2025 開催のお知らせ
ノーコード推進協会(NCPA)では2025年2月7日(金)に「ノーコードシンポジウム」を共済で開催いたします。 “ノーコードの本質的価値と可能性を考える” 「ノーコードで誰でも作れる」、これまで広…
『全体最適化に向けて』の動画を公開しました
2025年1月10日にノーコード推進協会の主催で開催しましたオンラインイベント、「全体最適化に向けて」の動画を公開いたしました。
NPCAが、TechGALAコミュニティサポーターに
一般社団法人 ノーコード推進協会は、TechGALAコミュニティサポーターに認定されました。 2025年2月に開催される、TechGALAを盛り上げるべく、弊団体からも会員の参加を促します。
1/10 オンライン対談セミナー『全体最適化に向けて』開催のお知らせ
昨今の物価上昇や現在・今後の人財不足などに対応すべく、費用をより安くすること、およびより少ない人数でも仕事のスピードと質を維持または改善できるようにすることはどの企業でも共通の課題です。本セミナーでは、それら企業成長に必要な条件を満たす手段として、FPTという会社からFPT自社開発製品のうちワークフロー特化型ノーコードツールであるFezyFlowまでを事例やデモなどを含みご紹介いたします。
『人とAIエージェントが描く、新しい成功のカタチ 〜 Salesforceの自律型AIの全貌を紹介』の動画を公開しました
2024年12月13日にノーコード推進協会の主催で開催しましたオンラインイベント、「人とAIエージェントが描く、新しい成功のカタチ 〜 Salesforceの自律型AIの全貌を紹介」の動画を公開いたしました。
【12/26開催】生成AI協会(GAIS)主催イベントにNCPAが後援、NCPA地方創生部会 部会長 佐藤氏が登壇します
一般社団法人 生成AI協会(GAIS)が主催する12月26日の勉強会にて、自治体DXと地方創生を考える勉強会が開催されます。このイベントにNCPAとして後援、地方創生部会 部会長の佐藤氏にご登壇いただくことになりましたの…
一般社団法人ノーコード推進協会が新理事体制で3期目をスタート
報道発表資料 2024年11月20日ノーコード推進協会 一般社団法人ノーコード推進協会が新理事体制で3期目をスタート新たに5人の新任理事を迎え理事会は8名体制へ 2024年11月18日にサイボウズ日本橋本社にて開催された…
12/13 オンライン対談セミナー『人とAIエージェントが描く、新しい成功のカタチ 〜 Salesforceの自律型AIの全貌を紹介』開催のお知らせ
私たちのビジネスを取り巻く環境は急速な勢いで変化しており、特に昨今では生成 AI が業務の生産性を向上させたり、ビジネスで成果を上げるためのアプローチとして各企業に注目され始めています。一方で生成AIを実際の業務で効果的に活用するケースはまだまだ限られており、AI に対する信頼性やセキュリティへの不安、AIを活用することによる新しい働き方への懸念、自社AI構築への多額の投資など、AIを業務で活用し、企業の成果に繋げていくに当たっての課題感を持つ企業も少なくありません。
SalesforceはNo.1のCRMサービスを提供しており、営業やサービス、マーケティング、コマース、データ分析などあらゆるCRMアプリケーションに組み込まれた形ですぐに効果的に利用できる「ビジネスのためのAI」を提供しています。
AIのトレンドは生成AIから新しい流れである「自律型AI」の時代が来ています。Salesforceが提供する自律型AIを搭載した新しいサービス「Agentforce」が、今後どのように業務で活用され、成果を上げていくことができるのか、その成功のカタチについてご紹介致します。
『NOCODE Summit 2024 in France 視察報告』の動画を公開しました
2024年11月15日にノーコード推進協会の主催で開催しましたオンラインイベント、「NOCODE Summit 2024 in France 視察報告」の動画を公開いたしました。
全国15自治体が地域課題にノーコードで挑む!ノーコード宣言シティーサミット2024 開催報告
報道発表資料 2024年11月05日ノーコード推進協会 2024年10月24日(木)、一般社団法人ノーコード推進協会(以下NCPA、代表理事:中山五輪男) は「ノーコード宣言シティーサミット2024」を開催いたしました。…